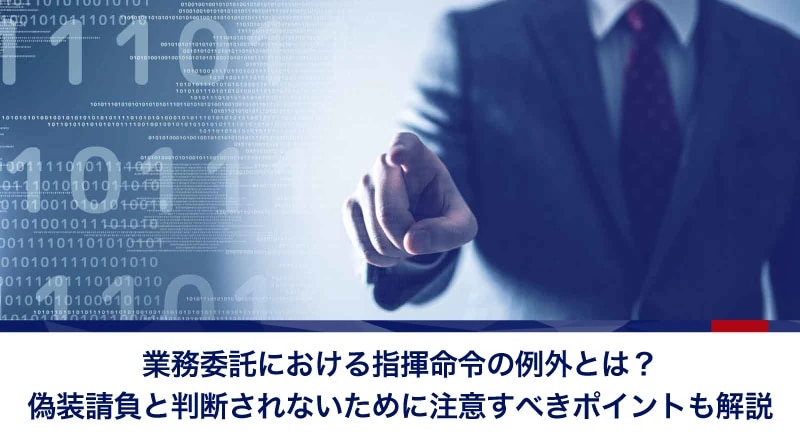
業務委託における指揮命令の例外とは?偽装請負と判断されないために注意すべきポイントも解説
業務委託契約では、労働者に対しての指揮命令をすべて受託者が行わなければなりません。この規則を破った場合、偽装請負に該当してしまい、罰則の対象となる可能性があります。本記事では、業務委託の指揮命令や、指揮・指示が例外として認められる条件について紹介します。業務委託で人材を確保する際には、指揮命令の基本と例外について確認しておきましょう。
目次[非表示]
- 1.そもそも業務委託の指揮命令とは
- 2.業務委託契約における指揮命令・指示の例外と認定されるパターン
- 2.1.適法な指示命令だと認められるもの
- 2.2.指揮命令・指示以外の行為
- 3.指揮命令・指示の例外として認められる条件
- 3.1.緊急事態に関する要件
- 3.2.業務内容の変更における指示
- 3.3.法令順守に必要な指示
- 3.4.業務手順に関する指示
- 4.厚生労働省が定める偽装請負のパターン
- 5.偽装請負となった場合の罰則
- 5.1.職業安定法違反の罰則
- 5.2.労働者派遣法違反の罰則
- 5.3.労働基準法違反の罰則
- 6.まとめ
そもそも業務委託の指揮命令とは
業務委託における指揮命令とは、「労働者に対して使用者側が指揮監督し命令できる権利」のことです。原則として、指揮命令の対象となるのは雇用関係にある人のみとなります。業務委託契約の場合、受託者と委託者の間には、雇用関係が成立しません。そのため、委託者が受託者に対して、仕事の内容を指定するなどの指揮命令を行うと、「偽装請負」と判断されて罰則の対象になるリスクがあります。
業務委託における「指揮命令」と「指示」の違い
業務委託における「指示」とは、仕事の方法や業務に関するやり方を指し示すことを意味します。業務に必要な指示を行うことで、効率化やトラブルを防止することが目的になり得ます。受託者に対して指揮監督を行って命令できる権利が指揮命令とは異なり、業務を委託した側がその場で業務の指示を出せる点が特徴です。
それぞれの違いは関係ない
業務委託では、委託契約に基づいて委託業務を受ける側が、自己の判断で業務を遂行することが原則です。一方で、指示は必要に応じて出されるものであるため、業務委託においては委託者が直接指揮命令を行うことは避けなければなりません。したがって、業務委託においては指揮命令と指示の違いに限らず、受託者への命令全般は基本的には禁止されていると考えるべきでしょう。
業務委託における委託元の指揮命令・指示は違法行為
業務委託契約では、受託者が独自の裁量で業務を行うことが認められています。それにも関わらず指揮命令・指示があった場合には、業務委託が偽装請負として認定され、違法契約とみなされる可能性があります。偽装請負となれば、罰則の対象となるため大きなトラブルに発展する懸念もあります。業務委託をする際には、正社員と同等の指揮命令・指示を行うことは禁止されていると、全社で理解しておくことが必要です。
業務委託契約における指揮命令・指示の例外と認定されるパターン
業務委託契約における指揮命令・指示は、原則として禁止されています。一方で、指揮命令・指示に該当するものでも、例外と認定されるパターンもあります。以下では、業務委託契約における指揮命令・指示の例外について解説します。
適法な指示命令だと認められるもの
業務委託契約においても、適法な指示命令だと認められるものに関しては、例外として指揮命令・指示が許容されます。例えば、以下の指揮命令・指示などは、適法なものと認定される可能性があります。
- 安全に配慮した作業の実施方法
- 納品物の品質確保のための指示
- 納期の調整に関する指示
- 委託業務の実施に必要な情報提供
- 予め決められたルール・マニュアルの遵守を求める指示
業務委託契約で指揮命令・指示が必要だと判断される場合には、上記のケースに当てはまるか確認することがポイントです。
指揮命令・指示以外の行為
報告義務や情報提供の要請、委託者からの業務状況や進捗状況の報告、必要な情報提供の要請などは、委託契約における指揮命令・指示とは異なります。そのため、業務委託の受託者に対して、これらの行為をしても問題にはなりません。業務の品質確認や確認・検収も、契約内容を確認することが目的であるため、指揮命令・指示以外の行為に該当します。
そのほか、業務委託契約に基づく報酬の支払いも、委託者からの指揮命令・指示ではなく、契約の報酬支払い義務に基づく内容であるため例外です。
指揮命令・指示の例外として認められる条件
業務委託において指揮命令・指示の例外として認められるには、いくつかの条件があります。以下では、指揮命令・指示の例外として認められる条件についての詳細を解説します。
緊急事態に関する要件
業務委託で働く人に対して、緊急事態に関する要件が発生した場合、指揮命令・指示の例外条件として認められています。例えば、労働者が急病やケガなどによって業務が困難となった場合、受託者に対して指揮命令・指示を出すことが可能です。一方で、緊急事態があったとしても、常に指揮命令・指示を出すことが許容されるわけではありません。状況に応じた判断が必要となるため、事前に判断基準を設けておくことが重要です。
業務内容の変更における指示
業務内容に変更が生じた場合、使用者は指揮命令により、変更後の業務内容に基づく指示をすることが可能です。例えば、契約先が新しい業務を依頼した場合、使用者は最新の事情に関する指示を受託者に実行できます。しかし、指示内容が契約内容と異なる場合や、業務の範囲を超えた指示に関しては、従来通り禁止されています。
法令順守に必要な指示
「法令順守に必要な指示」とは、使用者が法令を遵守するために必要な指示のことを指します。一般的には安全衛生に関する指示や、著作権法に基づく指示などが、「法令順守に必要な指示」に該当します。法令順守に必要な指示は、労働者派遣法違反や職業安定法違反などの問題を防ぐために必要であるため、例外として指揮命令・指示が認められています。
業務手順に関する指示
業務に必要な手順や作業の進め方について、具体的に指示をすることも指揮命令・指示の例外に含まれます。例えば学校給食調理業務の発注者が「調理業務指示書」を作成し、献立ごとの材料、調理方法、温度設定等を請負事業主に示すことなどは、問題ないと判断されます。このような業務手順に関する指示は指揮命令とは異なり、派遣先からの具体的な業務内容の指示として扱われて、適法とされる場合があります。
※参考:労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
厚生労働省が定める偽装請負のパターン
業務委託を活用する際には、偽装請負の疑いをかけられないように、細心の注意を払う必要があります。以下では、厚生労働省が定める偽装請負のパターンについて解説します。
形式だけ責任型
形式だけ責任型とは、作業現場の管理者が委託者の指示をそのまま伝えて、偽装請負になるケースです。業務委託という労働形態と、指揮命令・指示に関する理解不足から、頻繁に発生する構図として注意喚起がされています。特に単純作業においては、作業現場の管理者が手間を省くために、指示をそのまま伝えるケースが多いでしょう。現場の管理者に対しては、指揮命令・指示の基準についてしっかりと理解させることが重要です。
代表型
代表型とは、業務委託契約を結んでいるのに、作業者に対して細かい指示を出したり、時間の管理を行ったりするケースです。細かな指示を出すことは、受託者の自由な業務を妨げるだけでなく、偽装請負につながるリスクがあります。業務委託を活用する際には、ある程度受託者に業務の方法や仕事のペース配分は任せて、こちらから過度な要求はしないように注意しましょう。
使用者不明型
使用者不明型とは、何社も介して委託を繰り返し、直接的な指揮命令関係にない会社が、労働者に対して指示を行うケースです。例えば、A社がB社に委託した業務をC社へ業務委託した場合、C社に勤める労働者がA社やB社の指示を仰いで動くと、偽装請負となる場合があります。複数の会社を巻き込んだ事業展開を実施する際に、業務委託で人材を活用する場合には、この使用者不明型による不正に注意が必要です。
一人請負型
一人請負型とは、受託者に対して他社で働くように指示した場合に適用される偽装請負のパターンです。他社で働くように指示したにもかかわらず、労働契約ではなく業務委託契約を結んで命令を下している場合、偽装請負と認定される可能性があります。業務委託においては、企業が個人に対して事細かに指示を出すことは禁止されています。直接指示を出して事業を進めたい場合には、雇用契約を結ぶ必要があります。
偽装請負となった場合の罰則
業務委託をしていながら偽装請負と認定された場合、以下の罰則が科せられます。リスクの高さを理解するためにも、以下で偽装請負における罰則の詳細を確認しておきましょう。
職業安定法違反の罰則
偽装請負は職業安定法に違反し、懲役または罰金の対象となります。偽装請負による罰則は、職業安定法第63条から67条に基づき、事業者双方に対して、「1年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」が科せられます。決して軽い罰則ではないため、注意不足による指揮命令・指示の実行が、企業に大きな損失を与える可能性があります。
労働者派遣法違反の罰則
偽装請負と認定された場合、労働者派遣法違反の罰則において、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に科せられる可能性もあります。罰則の対象は、派遣先事業主と派遣元事業主の双方に及びます。どちらかのミスや理解不足が、相手企業に多大な迷惑を与える可能性があります。業務委託を活用する際には、相手企業が抱えるリスクも考慮して、偽装請負について理解を深めておきましょう。
労働基準法違反の罰則
労働者の供給によって利益を得ている場合、労働基準法違反の罰則も適用されます。供給元の企業に対して、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。悪質性によって罰則の条件が変わるため、明確な基準がないことは把握しておきましょう。
まとめ
業務委託を活用する際には、指揮命令・指示について深い理解が必要です。指揮命令・指示を出したことによって、偽装請負の疑いをかけられ、多大な損害を被る可能性があります。業務委託を正しく利用するためにも、指揮命令・指示の基本はしっかりと把握しておきましょう。同時に、業務委託における指揮命令・指示には例外も存在します。状況次第では例外として指揮命令・指示を出せるケースもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。業務委託を検討する際には、派遣サービスでの代用も考えられます。
「アイエスエフネットのITインフラエンジニア派遣サービス」では、高いスキルと豊富な経験を持つエンジニアを多数採用しています、派遣契約であれば指揮命令・指示のリスクを考慮することなく、必要に応じて適切な命令が出せます。事業において柔軟な対応が可能になるため、この機会にアイエスエフネットのITインフラエンジニア派遣サービスでぜひ派遣の利用をご検討ください。
アイエスエフネットのITインフラエンジニア派遣サービスの問い合わせはこちら
アイエスエフネットがIT担当者の課題を解決!









